- 集 合 鹿背山分校 9:00
- 時 間 9:00~12:00
- 服 装 作業する服装 水筒持参
第213回 鹿背山城の整備
2016/12/1
— posted by kanri at 06:11 pm
鹿背山城跡の現況を点検しました
2016/11/24
こんにちは。鹿背山城プロジェクトチームのKです。
去る11月3日(祝)、今シーズンの鹿背山城跡の整備活動に備え、現状を確認するために城跡に登りました。
会員諸兄姉向けには今後の活動の資料として、また、鹿背山城跡見学者の皆様には散策時のご参考の為に、簡単にご報告いたします。
今年の木津川市内の社寺の秘仏・秘法特別開扉には鹿背山城麓の西念寺さんも参加されていました。
西念寺さんへの参拝は後にして、まずは大手道から主郭へ向けて登っていきます。途中、たびたび倒竹が道に横たわっていましたので、一人で除けられるものは除けておきました。



天気が良く、主郭Ⅰからは木津の町が良く見えましたが、春に設置した吹き流しが写真撮影には、少し邪魔になるのかも知れません。
木津の町から鹿背山城の位置を把握しやすくする狙いで掲げた吹き流しですが、常設については再考した方が良さそうです。

他にも取付ネジの緩みなどがありました。全数の点検と、破損部品の取替が必要になりそうです。


また、主郭Ⅰの東側から背後の水の手へルートが例年になく笹藪と化していました。


これらはチェーンソーなどを使った複数人での作業が必要です。散策中に遭遇した場合は無理せずに来た道を引き返すなどしてください。

またここから伐竹保管場所への谷筋もすっかり若い竹に覆われつつあります。ここは春の筍蹴りが行き届かなかった場所だと思います。

枝の細い木なので、比較的容易に除去できると思います。重要な散策路ですので、優先的に手を付けるべき場所だと思われます。

以上、主な遺構と散策路を重点的に見てまわりました。その他、プロジェクトチームおよび会員の方で整備や散策時にお気づきのことがありましたら、他のメンバーと意見を交わして下さい。
また散策に来られた方でご意見がありましたら、山麓の西念寺さんの前に設置している登山ノートにご記入ください。
(なお、ご意見は整備の際の参考にはさせて頂きますが、ご返答はいたしかねます。)
整備や散策の際には安全第一で、無理なく鹿背山城を楽しみましょう。
— posted by 小大豆 at 03:02 pm
郷土の食を知る「茶粥会と座談会・講演会」
2016/10/16
10月9日(日)に『郷土の食を知る「茶粥会と座談会・講演会」』があり参加しました。
白粥の経験しかなかった私には、興味深く”どんなものかな~”と期待しておりましたが、案外あっさりとした食感に”こんなものか”といささかガッカリ?。
しかし、添え物の梅干し、おしんこ、かまぼこ、煮物等のおかずを食すことにより、茶粥の味が引立ち、気が付けば粥の椀が空っぽになってました。”美味しかった”と感激に侵っていると、なんだか胸のあたりが熱なり、同席の方も同じような感想を文述べられたので、”なる程、活力の源になるんだ”と茶粥の底力を再発見したした次第です。


其の後、意見交換があり、途中から講演を予定せれていた「冨岡典子先生」も同席され、地方の習慣や、祖父母からの伝承による茶粥の体験談等をを拝聴し、食文化や、纏わるエピソード等を興味深く聴かせていただきました。
最後は、「冨岡典子先生」の「大和の茶粥は1300年の食遺産」の講演があり、茶粥の歴史から作り方、地方の特色(伝承により異なる)、東大寺修二会の修行僧が供する”茶粥”「ごぼう」等、知らなかった事象の説明に感激いたしました。
食文化は、後世に伝える義務が私達に課せられている事を知り、茶粥の集い第2弾を期待しています。
— posted by kanri at 06:48 am
第2回 鹿背山城何でも知ろう連続講座「城整備」
2016/10/1
- スケジュール
9:00 JR木津駅西側 バス停前集合 鹿背山城へ(徒歩)
9:30 鹿背山分校着(会員は直接校庭 集合可)
10:40 午前 鹿背山城 城整備開始~12:00 昼食
12:50 午後 鹿背山城 城整備開始~15:00 城整備終了
15:10 城整備後の反省会(鹿背山会館)
15:40 現地解散 - 持ち物:昼食・飲み物・帽子・軍手・筆記具など
(整備道具類は当方で用意いたします) - 参加申込:ホームページ

またはFAX:0774-72-0014(木津の文化財と緑を守る会) - その他:会員の参加申込は不要。
— posted by kanri at 05:26 pm
第84回 『ふれあい文化講座』
※守る会全役員は準備のため12時集合
ご都合の悪い方は必ず岩井までご連絡下さい。
- 場 所 中央交流会館(いずみホール)
- 時 間 開演13:30~16:3分頃(開場13:00分から)
- 演 題 「浄瑠璃寺の建築と庭園」― その信仰と美 ―
- 講 師 冨島 義幸 先生(京都大学大学院准教授)
- 演 題 「難波京の変遷をたどる」
- 講 師 積山 洋 先生(大阪文化財研究所)
- その他 参加料 無料 事前申し込みはいりません
- 主 催 木津の文化財と緑を守る会・木津川市・興福寺
— posted by kanri at 05:25 pm
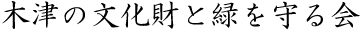










Comments